年金分割
年金分割制度とは
離婚する際に厚生年金や共済年金(以下「厚生年金等」といいます)の分割制度を利用することができます。
この分割制度により、婚姻期間等一定の期間の厚生年金等の保険料納付実績(標準報酬等)が分割されます。
この分割を受けた側は、分割を受けた分の保険料を納付したとして扱われ、離婚当事者それぞれの老齢厚生年金等の年金額は、分割後の記録に基づいて計算されることとなります。
当事者間の合意や裁判で分割の割合を定めたとしても、年金事務所に対し分割の請求をしないと、年金分割をしたものとして取り扱われません。
また、原則として離婚が成立した時から2年を経過するまでに、年金事務所に分割の請求をしないと、年金分割が受けられなくなります。
年金分割制度の種類
年金分割制度の種類
| 年金分割の割合を決める方法 | 手続きの種類 |
|---|---|
| 当事者間の合意 | 合意分割制度 |
| 裁判手続(裁判外で合意できない場合) | |
| 平成20年4月1日以降に 被扶養配偶者である期間がある場合(注) |
合意分割制度 |
| 3号分割制度 |
(注)両方の制度を利用することが必要になる場合もあります。
合意分割制度
当事者間の合意や裁判手続により年金分割の割合を定めた場合に、合意分割制度を利用できます。平成19年4月1日以降に離婚等した場合に限り、利用できます。
この制度では、婚姻期間中の厚生年金等の標準報酬等の保険料納付記録を分割することができます。
ただし、分割の割合には一定の制約があり、分割を受ける側の分割前の持ち分相当割合から2分の1までの範囲内で定めなければなりません。
また、合意で分割の割合を決めた場合、公正証書又は公証人の認証を受けた合意書によって分割の割合を明示し、この書類を年金事務所に提出する必要があります。
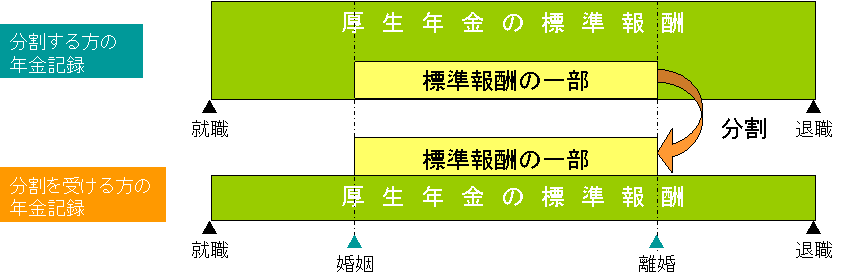
*平成19年4月1日以後に離婚した場合や事実婚関係を解消した場合など。
*平成20年4月1日以後に国民年金第3号被保険者期間があること。
*請求期限(原則として、離婚から2年以内)を経過していないこと。
3号分割制度
第3号被保険者であった者(たとえば,夫がサラリーマンで妻が専業主婦の場合の妻等が該当する)からの請求により、平成20年4月1日以降の相手方の厚生年金等の標準報酬等を自動的に2分の1ずつ分割する制度です。
この3号分割制度の場合、一方の当事者による請求で分割請求をすることができ、分割の合意や裁判が必要ありません。
この制度により分割される標準報酬は、婚姻期間のうち、平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の相手方の厚生年金等の標準報酬等で、保険料納付記録を分割することができます。
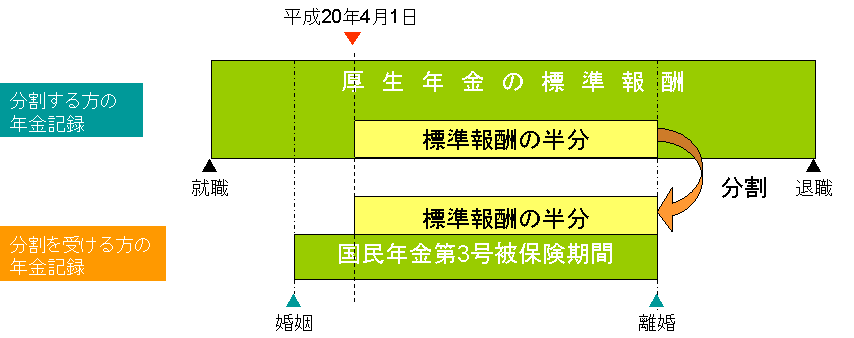
条件に該当する場合、合意分割制度に基づき分割することが出来ます。
*平成20年5月1日以後に離婚した場合など。
*平成20年4月1日以後に国民年金第3号被保険者期間があること。
*請求期限(原則として離婚から2年以内)を経過していないこと。
バナースペース
小杉悦子 行政書士事務所
〒362-0045
埼玉県上尾市向山3-46-1
携帯 070-6631-6432
TEL 048-781-7508
FAX 048-781-7508
業務時間
9:00〜17:00
休日:日・祝日
時間外、休日でも事前に
ご予約いただければご相談OK。
■埼玉県・東京都・千葉県
その他、ご相談ください。