財産分与
財産分与とは
離婚した者の一方が,他方に対して財産の分与を求めることができます。
- (1)夫婦が結婚中に協力して得た財産の清算
- (2)離婚後の経済的弱者に対する扶養料
- (3)相手方のせいで離婚を余議なくされたことについての慰謝料
離婚が成立してから2年経過すると財産分与の請求ができなくなります。
財産の清算
財産分与の対象となる財産の範囲
財産分与の対象となるのは、以下のふたつです。
- (1)名義は一方のみとなっているが、実質は夫婦が協力して得た財産(実質的共有財産)
- (2)名義も実質も夫婦の共有に属する財産(共有財産)
結婚している間に取得した財産は、財産分与の対象となる可能性が高くなります。
その一方で、名義も実質も一方のみが所有する財産(特有財産)は、原則として財産分与の対象とはなりません。
たとえば、夫が結婚前から所有していた財産や、夫が相続で取得した財産等は財産分与の対象とはなりません。
ただし、財産分与を請求する者が、他方配偶者の特有財産の形成・維持や減少防止に協力したとして、特有財産についても財産分与が認められる場合があります。
また、夫婦が個人経営をしている会社名義の財産や、夫の実家の家業に相応の報酬を受けずに従事していた場合に、この家業によって得られた夫の親の財産も財産分与の対象となる場合があります。
どのくらいの割合で財産分与をするのか
どのくらいの割合で財産を分けるかについては、財産形成,維持への寄与度によって異なります。
妻が専業主婦であるか否かにかかわらず、原則として財産分与割合を2分の1ずつと決められることが多いようです。
個別事情によって割合は変わり、妻の寄与度が夫よりも高い場合(婚姻費用も夫と同様に負担し長年妻が家事にも従事したという場合等)、妻の方が多額の財産分与を受けられる場合があります。
扶養料としての財産分与
この場合、夫婦財産を清算し慰謝料を取得しても生活の維持が困難と認められる場合に、扶養料としての財産分与が認められる傾向にあります。
扶養料としての財産分与の場合、その額は、結婚期間、有責の程度、夫婦の資産・収入、夫婦の年齢、子どもの養育費、夫婦の病気等を総合的に考慮して決められます。
ただし、妻の再婚や死亡までの生活保障を認められることは少なく、離婚後、妻が安定した収入を得るまでの一定期間に限定される傾向にあります。
慰謝料的財産分与
慰謝料としての意味合いを込めた財産分与が認められる場合があります。
ただし、慰謝料請求と慰謝料的財産分与の請求の両方をした場合、取れる金額が2倍になるわけではなく、慰謝料的財産分与で得た金額が慰謝料の金額算定の際に考慮(減額)されます。
慰謝料・財産分与をいくらもらっているの?
では実際、慰謝料・財産分与はどのくらいになるのでしょうか。下記のグラフを参照してください。ただし、先述したとおり、さまざまな事情を考慮した結果になります。
慰謝料・財産分与
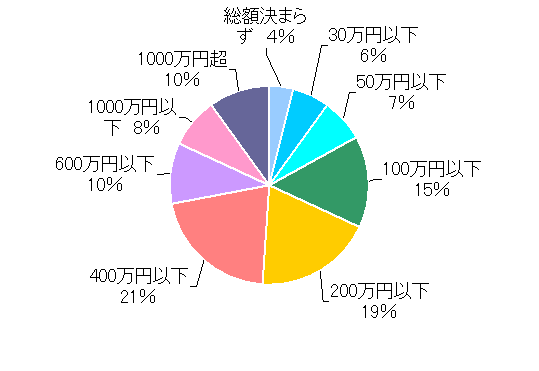
離婚後の請求
離婚の際、財産分与をしていなかった場合でも、離婚の成立から2年以内であれば離婚後に財産分与の請求ができる事もあります。
過去の婚姻費用
過去の婚姻費用については、離婚後の財産分与に含めることで請求できる事もあります。
ただし、離婚後2年が経過すると請求できなくなるため注意が必要です。
バナースペース
小杉悦子 行政書士事務所
〒362-0045
埼玉県上尾市向山3-46-1
携帯 070-6631-6432
TEL 048-781-7508
FAX 048-781-7508
業務時間
9:00〜17:00
休日:日・祝日
時間外、休日でも事前に
ご予約いただければご相談OK。
■埼玉県・東京都・千葉県
その他、ご相談ください。